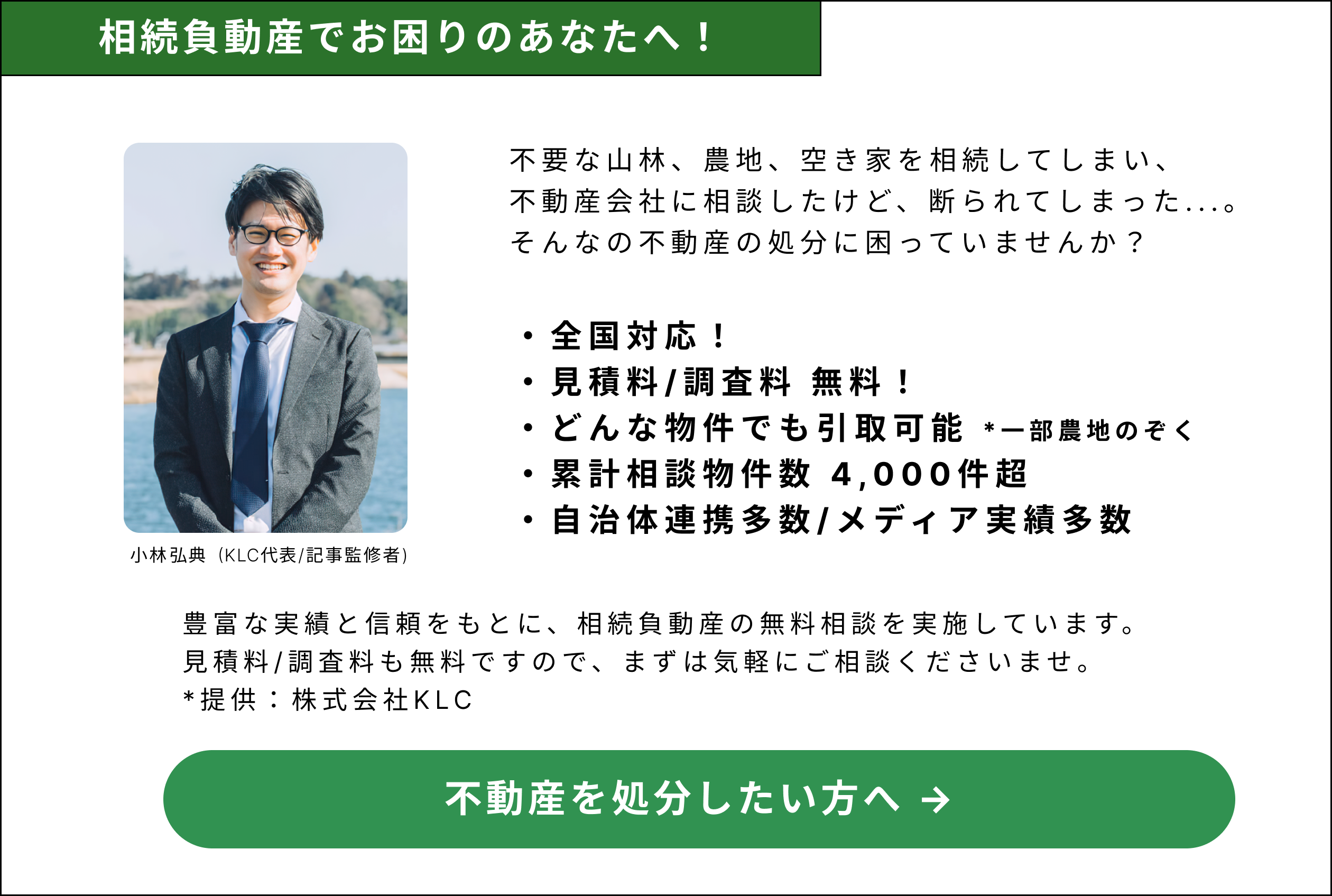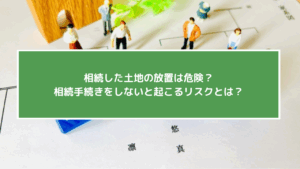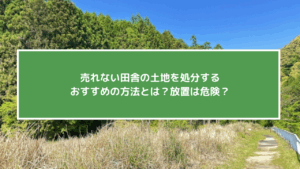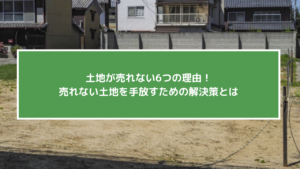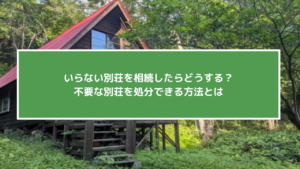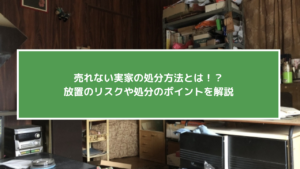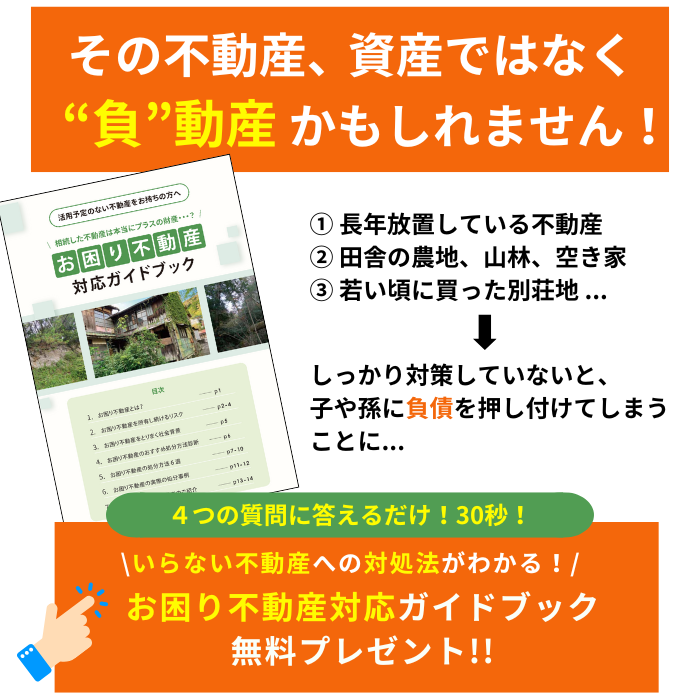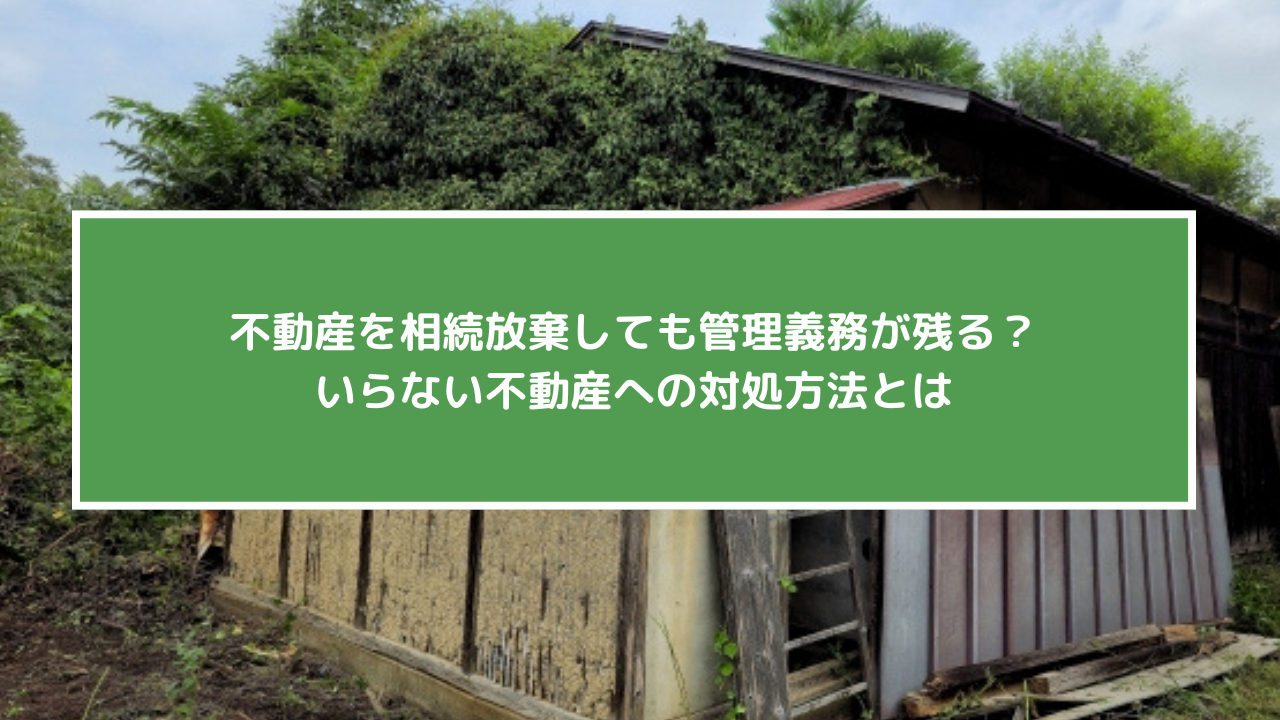
不動産を相続放棄しても管理義務が残る?いらない不動産への対処方法とは
相続等で、資産価値がなく活用できない不動産を所有することになってしまった場合、税金や維持・管理義務は大きな負担となります。そういった場合、不要な不動産の所有を避けるために、相続放棄を検討する方は少なくありません。しかし、相続放棄をしても不動産の保存義務が残ってしまう可能性があります。
今回は、不動産を相続放棄した場合の保存義務について解説するとともに、不要な不動産を相続した場合の最適な対処方法をご紹介します。
相続放棄すると不動産はどうなる?手放すことはできる?

相続放棄をすると、原則として不動産は次の相続人に引き継がれるため、不要な不動産は手放すことができます。しかし、相続放棄をしても不動産について保存義務を問われる場合があります。
相続放棄をしても保存義務が残る可能性がある
不要な不動産を手放す目的で相続放棄をしても、例外的に保存義務が残る場合があります。民法第九百四十条では、相続放棄をした際に、不動産を占有しているとみなされた場合、自己の財産と同様の注意をもって、財産を保存する義務があるとされています。
第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
占有とは、自己のために物を事実上支配している状態をさします。例えば、相続放棄をした時点で不動産に住んでいた、倉庫として使っていたという場合は、占有に該当する可能性があります。もし不安がある場合は、弁護士等の専門家に相談しましょう。
相続財産清算人(相続財産管理人)とは
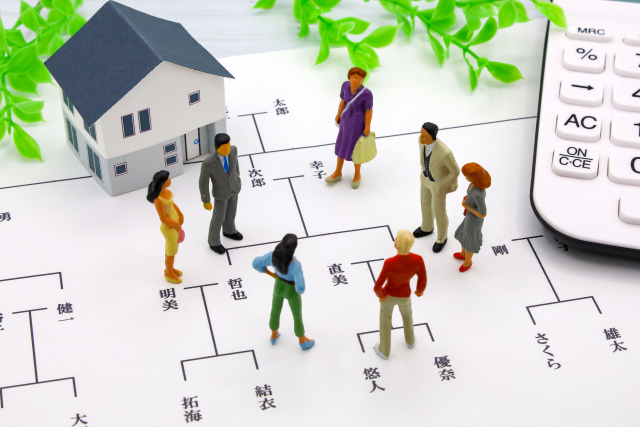
相続財産清算人とは、相続放棄が行われ次の順位の相続人が存在しない場合、家庭裁判所によって選任される、相続財産の管理・清算を行う人をさします。相続財産清算人は、相続人がいない財産を管理し、国庫に帰属する役割を持ちます。以前は「相続財産管理人」と呼ばれていましたが、2023年4月の民法改正により相続財産清算人に名称が変更されました。
相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は、申立てにより相続財産の清算人を選任します。相続財産清算人は、被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。
相続財産清算人は、利害関係者(債権者、特定遺贈の受遺者など)または検察官が、家庭裁判所に申し立てることで選任の手続きが始まります。もし、相続放棄をして自分の次に相続人がいないという場合は、必要となる場合があります
相続財産清算人(相続財産管理人)の選任が必要なケースとは
相続財産清算人の選任が必要となるのは、相続不動産の保存義務が発生する状況で、相続放棄をし、次の相続人がいない場合です。このようなケースでは、相続不動産に関する保存義務を問われる可能性があるため、相続財産清算人の選任を申し立て、相続財産清算人に不動産を引き継ぐことで保存義務を免れることができます。
相続放棄を行った際に、相続財産について保存義務が発生する可能性がある場合は、相続財産清算人の申し立てを検討しましょう。なお、相続財産清算人の選任申立てには裁判所が定める一定額の予納金が必要となる点に注意しましょう。
相続放棄で損をしないための注意点とは?

相続放棄は、不要な不動産の相続を避けるために有効な手段ですが、状況によっては相続放棄により損をする可能性があります。ここでは、相続放棄で失敗しないための注意点を解説します。
いらない不動産だけを放棄することはできない
相続放棄では、不要な財産を選んで放棄することはできません。そのため、価値のない不動産や借金は放棄したいけれど、預貯金や株式といった財産は相続したい、といった選択は認められません。
相続放棄をする場合は、資産価値のある財産や負債も含めて、一切の遺産を相続する権利を手放すことになります。そのため、相続放棄を検討する際は、まず被相続人の財産全体を正確に調査し、検討することが重要です。財産調査の結果、プラスの財産が多いのであれば、相続後に不要な不動産を処分するといった選択を検討しましょう。
相続放棄ができる期限は三か月以内
相続放棄の手続きには、期限が設けられています。具体的には、自己のために相続の開始があったことを知った時から三か月以内に行使する必要があり、その間に相続するか放棄するかを決め、家庭裁判所に申述をしなければなりません。
この期間を過ぎてしまうと、原則として相続を承認したものとみなされ、相続放棄はできなくなります。財産調査等に時間がかかり、3ヶ月以内に判断ができない場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることで、期間を延長できる場合もありますので、早めに専門家へ相談しましょう。
次の相続人に連絡をしておく
相続放棄をすると、相続権は次の順位の相続人に移ります。例えば、第一順位である子が相続放棄をすると、第二順位である被相続人の親、親が亡くなっていれば第三順位である兄弟姉妹へと相続権が移っていきます。
相続放棄したことを次の相続人に伝える法的な義務はありませんが、もし相続放棄をしたことを次の相続人が知らないままに不要な不動産が引き継がれてしまった場合、トラブルになる可能性もあります。相続放棄を行う場合は、トラブルを避けるために次の相続人に連絡することをおすすめします。
不動産の管理義務を怠ると起こるリスクとは

相続放棄を検討するような不要な不動産を相続した場合、売却もできず活用もできないといった状況で、不動産をそのまま放置してしまうケースも少なくありません。
しかし、不動産を適切に維持・管理せずに放置することは、さまざまなリスクを引き起こす可能性があります。ここでは、不動産を放置した場合に起こる具体的な3つのリスクについて解説します。
金銭面のリスク
不要な不動産を所有することは、金銭的なリスクを負うことにつながります。不動産を所有していれば、収益の有無に関わらず固定資産税が毎年発生します。管理を怠った不動産が原因で第三者に損害を与えた場合、損害賠償責任を問われる可能性があります。例えば、老朽化した建物や外壁が崩れて、隣人や通行人に怪我をさせた場合、損害賠償請求をされることも考えられます。
また、土地の管理を怠り、庭木等が道路にはみ出して事故の原因となってしまったという場合も、管理者責任を問われる可能性があります。
対人関係のリスク
適切に管理されていない不動産は、対人関係を悪化させる要因となります。不動産の管理を怠り、雑草が繁殖し害虫の発生や獣害の原因を作ってしまった場合、近隣住民から苦情を受ける可能性があります。その他にも、土地が荒れて隣地との境界が曖昧になり、近隣住民と土地の境界を巡って争いになることも考えられます。
また、不要な不動産を処分しないままに子や孫に引き継がれてしまうと、権利関係は複雑になり、ますます処分は難しくなります。最悪の場合は土地の押し付け合いが発生するなど、家族、親族同士のトラブルの原因になってしまいます。
犯罪発生のリスク
放置された空き家や空き地は、犯罪の温床となってしまうリスクがあります。人の出入りがなく管理されていないとみなされた土地は、不審者の侵入や不法占拠、放火のターゲットにされる可能性が高まります。
また、ゴミの不法投棄をされたり、最悪の場合は知らないうちに犯罪現場に利用されてしまい、警察に呼び出される、地域の治安悪化の原因を作ってしまうといったことも考えられます。
相続放棄できない不動産を処分する方法とは

相続の際に財産があり相続放棄ができない、または活用できない不動産を相続してしまったという場合、不動産の知識がない相続人が不要な不動産を手放す方法を見つけることは簡単ではありません。そこでここでは、相続放棄できない不動産の処分に使えるおすすめの方法をお伝えします。
不動産会社に依頼
不要な不動産がある場合に、まず検討するべき方法が不動産会社への売却依頼です。売却方法には大きく分けて「仲介」と「買取」の2種類があります。
仲介は、不動産会社に買主を探してもらう売却方法です。買主がみつからないなど、時間はかかる可能性がありますが、希望する価格で売却しやすいのがメリットです。買取は、不動産会社が直接その不動産を買い取る方法です。速やかに不動産を処分できる反面、売却価格は低めになる可能性があります。どちらの方法が適しているかは、不動産の状況や希望によって異なりますので、状況に合わせて選択しましょう。
自治体、法人等に寄付
不要な不動産を所有している場合は、寄付をすることも選択肢の一つです。寄付先としては、不動産が所在する自治体や、社会福祉法人、NPO法人、医療法人などが考えられます。不要な不動産を寄付できれば、固定資産税や維持・管理の負担から解放されます。
注意点として、相続人も不要と感じるような不動産は、寄付が出来ないケースがあります。自治体や法人にとっては、寄付を受けることで管理コストが発生するため、利用価値のある不動産でなければ、受け入れを断られるケースがほとんどです。不動産によっては、寄付が難しい可能性もあることを把握しておきましょう。
相続土地国庫帰属制度
相続土地国庫帰属制度は、2023年4月にスタートした制度で、相続、または遺贈によって手にした土地を有償で国に引き取ってもらうことができる制度です。相続土地国庫帰属制度を使えば、必要な財産は相続しながら、不要な土地のみを手放すことができます。
ただし、利用できる土地には条件あり、建物が建っている土地や担保権が設定されている土地などは対象外となります。また、審査の結果不承認となった場合でも、審査手数料は返金されないため、利用する際はまず最寄りの法務局等に相談してみることをおすすめします。
有料引き取りサービス
売却や寄付等も難しく、不動産を処分する方法が見つからないという場合に使えるのが、不動産の有料引き取りサービスです。引き取り業者は、土地の引き取りに関する独自のノウハウや経験、専門知識をもっているため、その他の方法では引き取ってもらえなかったという土地でも、引き取ってもらえる可能性があります。
有料のサービスになりますが、税金や維持・管理の負担を負い続けることを考えれば、費用を払ってでも不動産を処分した方が特になるケースがほとんどです。有料引き取りサービスの中には、引き取りを装って他の投資詐欺に誘導するといった業者もあるため、依頼をする際は複数の業者を比較検討し、契約内容を十分に確認したうえで行うようにしましょう。

マッチングサービス
最近では、不動産を譲りたい人と貰いたい人を直接つなぐマッチングサービスも登場しています。マッチングサービスを利用すると、一般的な不動産市場では買い手が見つかりにくいような物件でも、ニッチなニーズを持つ買主の目に留まる可能性があります。
買い手が現れるまでに時間がかかる場合もありますが、時間をかけても希望価格でじっくり不動産を処分したいという方にはおすすめのサービスです。不要な不動産の処分に困っているという方は、まずは登録だけでもしてみることをおすすめします。
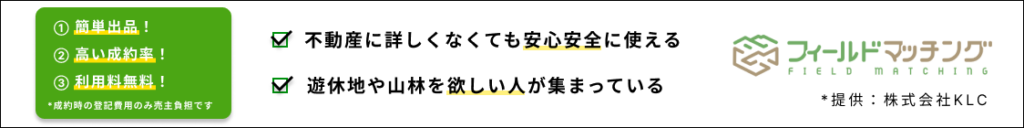
まとめ
今回は、相続放棄と不動産の関係や、不要な不動産を相続した場合の対処方法などについて解説しました。不要な不動産に困っていて相続放棄を検討しているという方は、ぜひ参考にしてみてください。
 監修者
監修者
株式会社KLC 代表 小林 弘典
幼少期から不動産が大好きな、自他共に認める不動産マニア。
不動産会社でも手を出せない不動産の専門会社「株式会社KLC」代表を勤め、
自身のYoutubeチャンネル「相続の鉄人」にて、負動産問題について啓蒙活動も実施。
- 総務省 地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業登録アドバイザー
- 空き家等低利用不動産流通推進協議会 理事
- 立命館大学経済学部 客員講師
- 不動産有料引取業協議会 代表理事