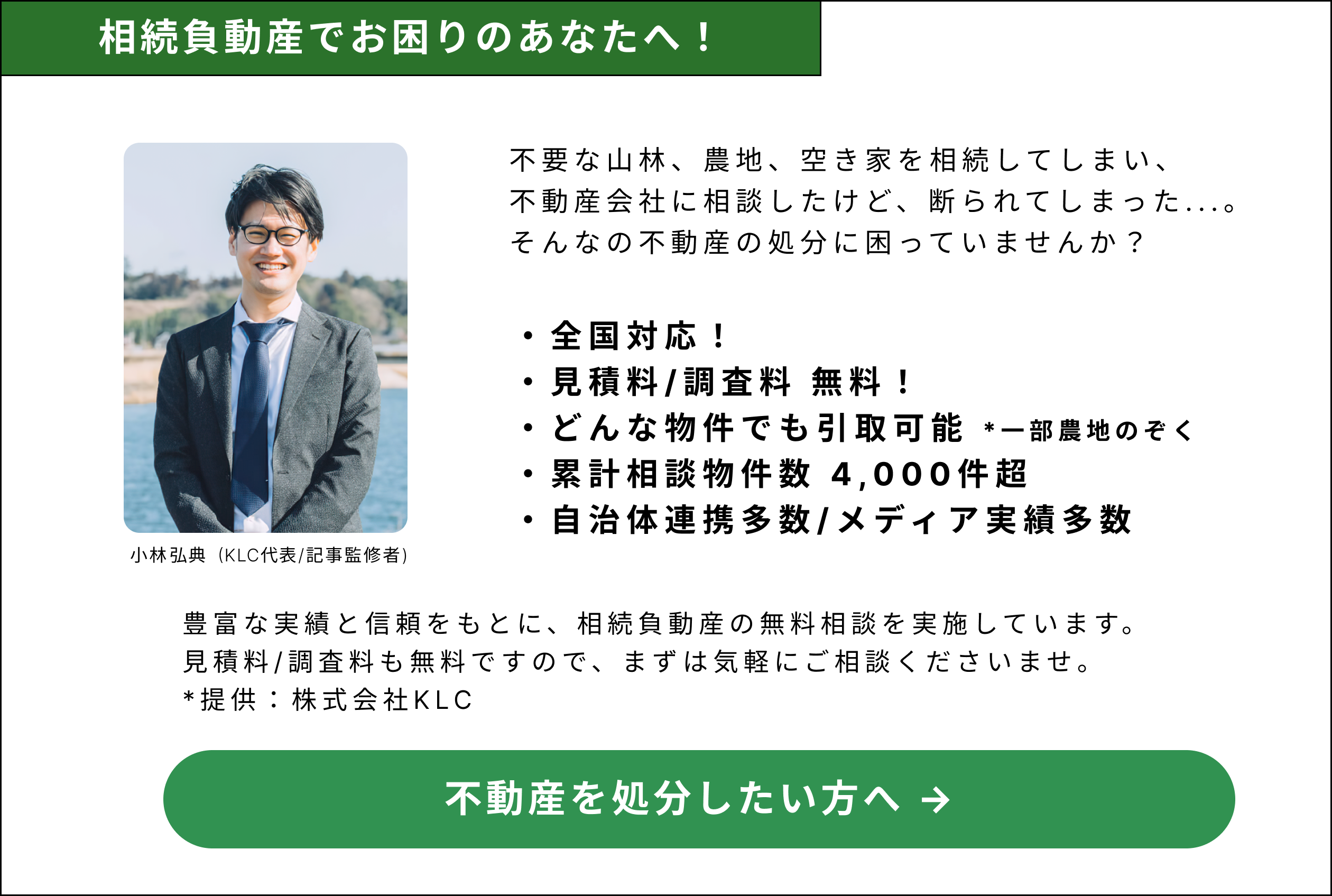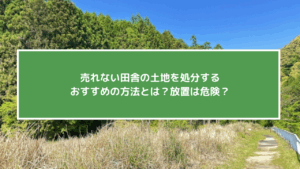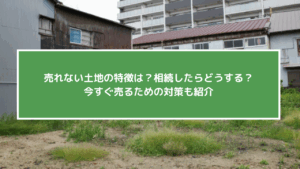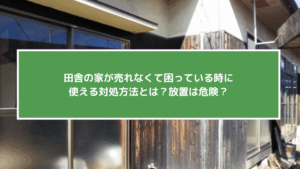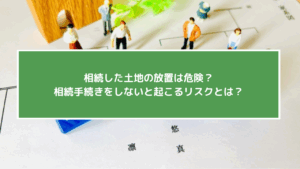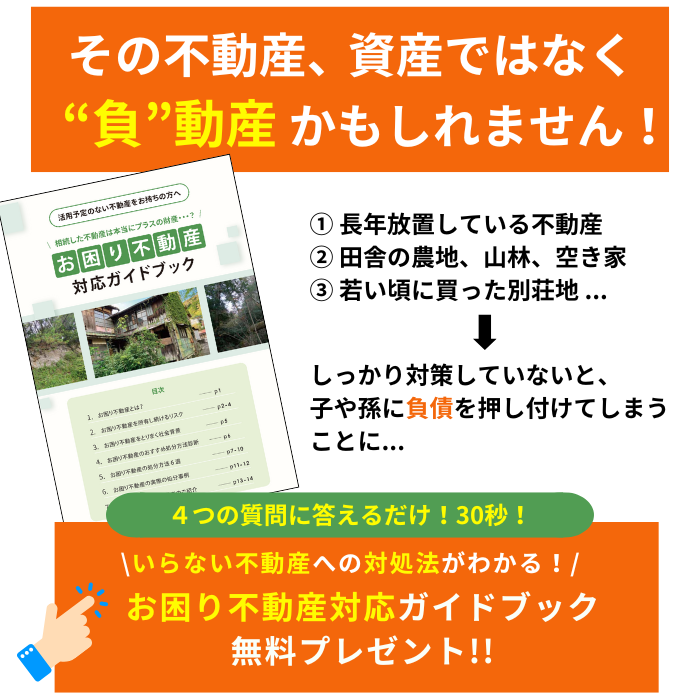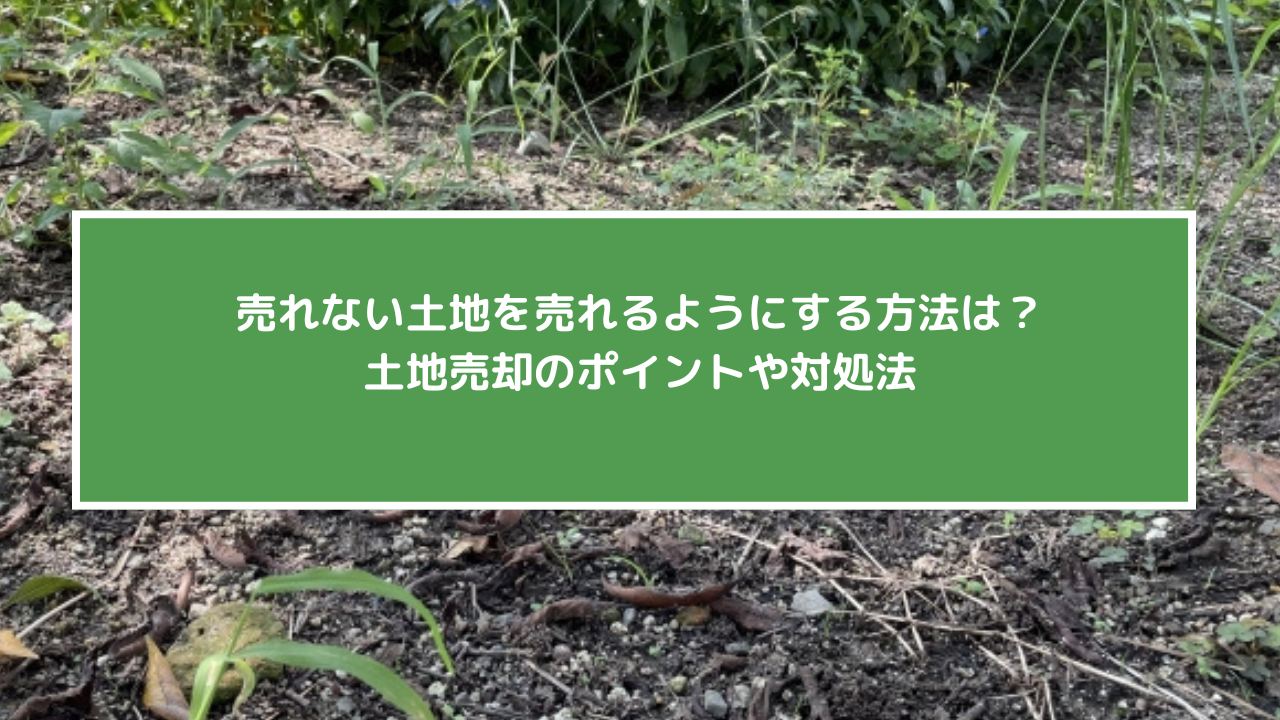
売れない土地を売れるようにする方法は?土地売却のポイントや対処法
相続で田舎の土地を意図せず所有することになり、売ろうにも買い手が見つからず、売れない土地に困っているという方が増えています。
本記事では、売れない土地を所有して困っている方のために、土地を売れるようにする方法や、売れなかった場合の対処方法など、役立つ情報を紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
土地が売れるまでの期間は?

土地は、売りに出してからどれくらいの期間売れなければ、売れない土地といえるのでしょうか。三か月たって売れ残っていれば、売れる見込みがないのか。それとも1年たっても売れ残っていれば、売れない土地なのか。売れない土地かどうかの見極めは、不動産の知識がないと判別が難しいところです。
土地が売れるまでの期間は、不動産の価格や売り出し時期によっても大きく変わってきますが、おおむね三か月程度が、土地の売り出しから成約までの平均的な期間となっています。
売りにだして三か月を超えても売れ残っている場合、「売れない土地」である可能性を考えてみてもいいかもしれません。
参考:公益財団法人東日本不動産流通機構「首都圏不動産流通市場の動向(2024年)」
こんな土地は要注意!?売れない土地によくある特徴5選
土地が売れないのには、理由があります。ここでは、売れない土地によくある特徴を紹介します。もし所有している土地にここで紹介する特徴が当てはまる場合は、注意が必要かもしれません。
立地が悪い
土地を売る上で最も重要なのが立地です。立地が悪ければ、どんなに広い土地であっても市街地など好立地の物件に比べて、売却難易度が高くなります。駅から遠い、周囲にインフラが整っていない、田舎にあり過疎地で人通りが少ないなど、不動産として活用が難しい立地の場合、なかなか売れない土地になる可能性が高いです。
接道が狭い・接道していない
土地が接道していない場合、接道環境のよい土地に比べて売れない土地になる可能性があります。土地まで接している道がなければ、土地にたどり着くことが困難となり、また道を整備する負担がかかることも考えられ、購入者からは敬遠されがちです。また、私道を通らないと土地にいけない場合も、私道の所有者とのトラブルになる可能性があるため土地を売ることが難しくなります。
権利関係が複雑
担保権が設定されている、境界が曖昧で土地の境界について隣人との間に争いがある、共同所有となっているなど、権利関係が複雑な土地は、活用をしようと思ってもまず権利関係を整理しなくてはならず、売れない可能性が高くなります。
農地、市街化調整区域など建物が建てられない
農地や市街化調整区域などで建物が建てられない場合、購入検討層が、建物を建てない前提の相手方に絞られる分、売れにくくなる可能性があります。法的な制限等で建物が建てられない場合、土地活用の選択肢が限定されてしまうため、買い手にとってもメリットがなく、土地が売れずらくなります。
傾斜地や旗竿地など形状が悪い
傾斜地や旗竿地など、形状が悪い土地は、平坦地や整形地に比べて、反響が減ってしまい、売れない場合があります。土地の形状が悪いと、土地を効率よく活用することが難しいです。傾斜地であれば、平らに整地する必要があるなど、買い主には大きな負担となります。土地の形状が悪いと、立地が良い土地であっても、売れる可能性は低くなります。
売れない土地を売却するためのポイントとは?

不動産会社に売却を断られてしまったなど、売れない土地であっても、工夫次第で売却の可能性をあげることができます。ここでは、売れない土地を売却するためのポイントを紹介します。
価格をさげる
土地が売れない場合、まず検討したいのが価格を下げることです。周辺の相場と比べて、土地の価格が割高になっていないかなどを確認しましょう。売れない土地を所有し、税金や管理義務の負担を負うことを考えたら、多少価格を下げてでも土地を手放した方が得することが多いです。
不動産会社を変更する
不動産会社を通じて売却依頼をしても土地が売れない場合、不動産会社の変更も検討しましょう。不動産会社が営業に力をいれていない場合、条件が良い土地であっても売れ残ってしまうことがあります。また、不動産会社によって得意な物件も違うため、会社を変更すると売れなかった土地でも売れる可能性があります。
土地を整備する
土地が荒れている場合は、草刈りをしたり、残置物を撤去するといった整備を行うようにしましょう。土地が整備されていないと、それだけで評価が下がってしまい、売れづらくなってしまいます。買主が負担を感じるポイントを少しでも減らしておくと、土地が売れる可能性も高くなります。
売れない土地を放置していると起こるリスクとは!?

土地が売れない場合、処分することを面倒だと感じて放置しているという方も多いかもしれません。しかし、土地を放置していると、税金の負担が続いたり対人トラブルなど、様々なリスクを抱えることになります。
税金の支払い、損害賠償請求
所有している土地が収益を生んでいない、または使用していない場合でも、固定資産税の支払いは発生します。また、土地の維持・管理責任からも逃れることはできません。適切な管理を怠り、建物が倒壊して通行人に怪我をさせるなど、土地が原因で周囲に損害を与えた場合、損害賠償を請求される可能性もあります。
隣人や親族との対人トラブル
土地の放置は、様々な対人トラブルを引き起こす原因になります。土地の雑草等が原因で害虫や獣害を起こし近隣住民から苦情を入れられる、土地が荒れて隣地との境界が曖昧になり所有を巡りトラブルになることもあります。また、土地が売れないまま相続された場合、子や孫の間で売れない土地の押し付け合いとなってしまいます。
犯罪に巻き込まれるリスク
土地を適切に管理していないと、最悪の場合、犯罪に巻き込まれてしまう可能性があります。周囲から管理されていないと思われた土地は、不法投棄の標的とされる場合があります。また空き巣や放火をされたり、犯罪現場に利用されるといった危険が発生します。
どうしても土地が売れない時のおすすめの対処法5選
土地が売れない、活用もできないという場合、土地の維持・管理や税金の支払いは大きな負担となります。そんな時は、少しでも値段を高くつけて売ることよりも、値段が付かなくてもとにかく早期売却を優先することで、結果的には将来的な負担を避けるという方針を検討してみても良いかもしれません。
隣人に譲渡する
不要な土地は、隣人に譲渡することを検討しましょう。隣人にとっては、土地がまとまって価値があがる、活用の選択肢が広がるといったメリットがあるため、実は受け入れてもらいやすい方法のうちの一つです。
連絡先がわからない場合は、法務局で登記謄本を取得し、住所を調べることができます。
相続土地国庫帰属制度を利用する
不要な土地は国に引き取ってもらうこともできます。相続土地国庫帰属制度は、遺贈、または相続によって手にした土地を有償で引き取って貰うことができる制度です。農地や山林といった活用が難しい土地でも引き取ってもらえるため、売れない土地を持っている場合は検討してみましょう。
相続土地国庫帰属制度は、引き取り後は国が管理するため、管理が難しい土地は引き取り対象となりません。また、審査の際にかかる審査手数料は、不承認となっても返金されない点に注意しましょう。
自治体に寄付
自治体に寄付をするのも、いらない土地を手放す方法として有効です。自治体によっては、土地や不動産の寄付を受け付けている場合があるため、役所の管財課等に問い合わせてみましょう。
ただし、自治体に寄付をした土地は、自治体が再活用をするため、立地が悪い等、条件が悪い土地は引き受けてもらえない可能性があります。
引き取りサービスを利用する
土地が売却ができず、その他の方法でも処分できない時に検討したいのが、不動産の引き取りサービスです。不動産の引き取りサービスは、不要な土地の処分に専門の知識やノウハウを持っているため、他の方法では売却を断られてしまった土地であっても、引き取ってもらえる可能性があります。
土地によっては、有料での引き取りになる場合もありますが、税金や維持・管理の負担を考えれば、有料でも土地を引き取ってもらうことは所有者にとってプラスとなります。売れない土地に困っているという方は、まずは相談だけでもしてみることをおすすめします。

マッチングサイトに登録する
マッチングサイトも不要な土地の処分としておすすめの方法です。マッチングサイトを使うことで、他の方法で断られてしまった土地であっても、全国の買い手に向けて情報を発信することができます。また、好きな価格で登録ができるため、時間をかけても少しでも高く土地を売りたいという方にはおすすめの方法です。
マッチングサイトは売買に関心が高い人があつまっているため、申し込みからの成約率が高くなっています。不要な不動産を少しでも高い価格で処分したいという方は、ぜひマッチングサイトを利用してみてください。
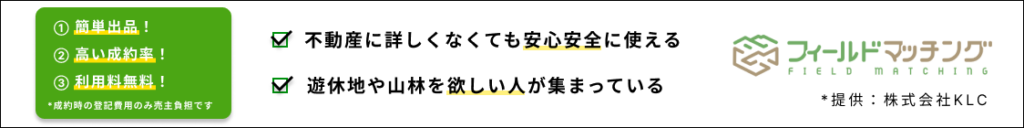
まとめ
本記事では、売れない土地を売却するポイントや売れない土地の処分方法などをお伝えしました。土地が売却できず、所有することが負担になっているという方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
 監修者
監修者
株式会社KLC 代表 小林 弘典
幼少期から不動産が大好きな、自他共に認める不動産マニア。
不動産会社でも手を出せない不動産の専門会社「株式会社KLC」代表を勤め、
自身のYoutubeチャンネル「相続の鉄人」にて、負動産問題について啓蒙活動も実施。
- 総務省 地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業登録アドバイザー
- 空き家等低利用不動産流通推進協議会 理事
- 立命館大学経済学部 客員講師
- 不動産有料引取業協議会 代表理事