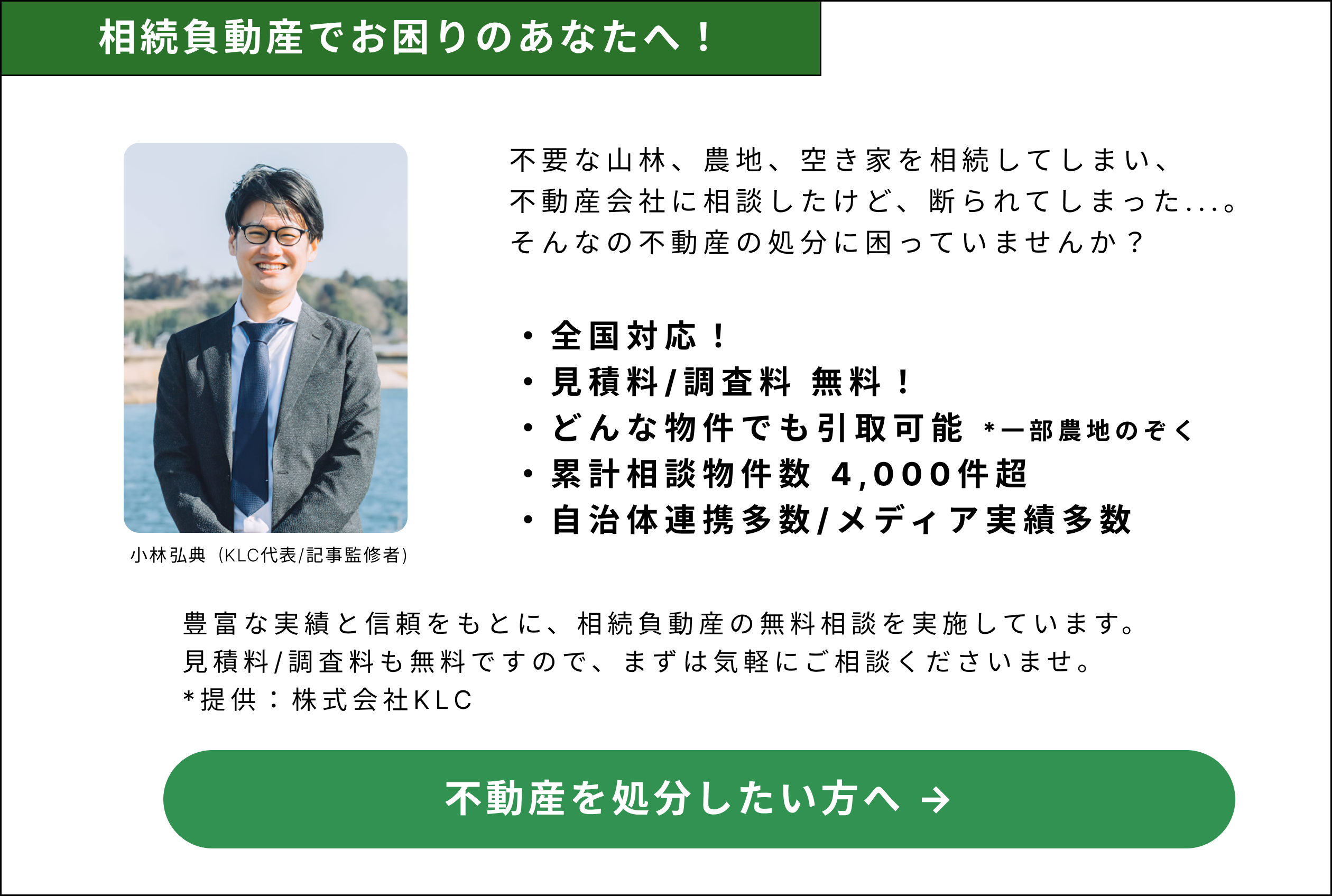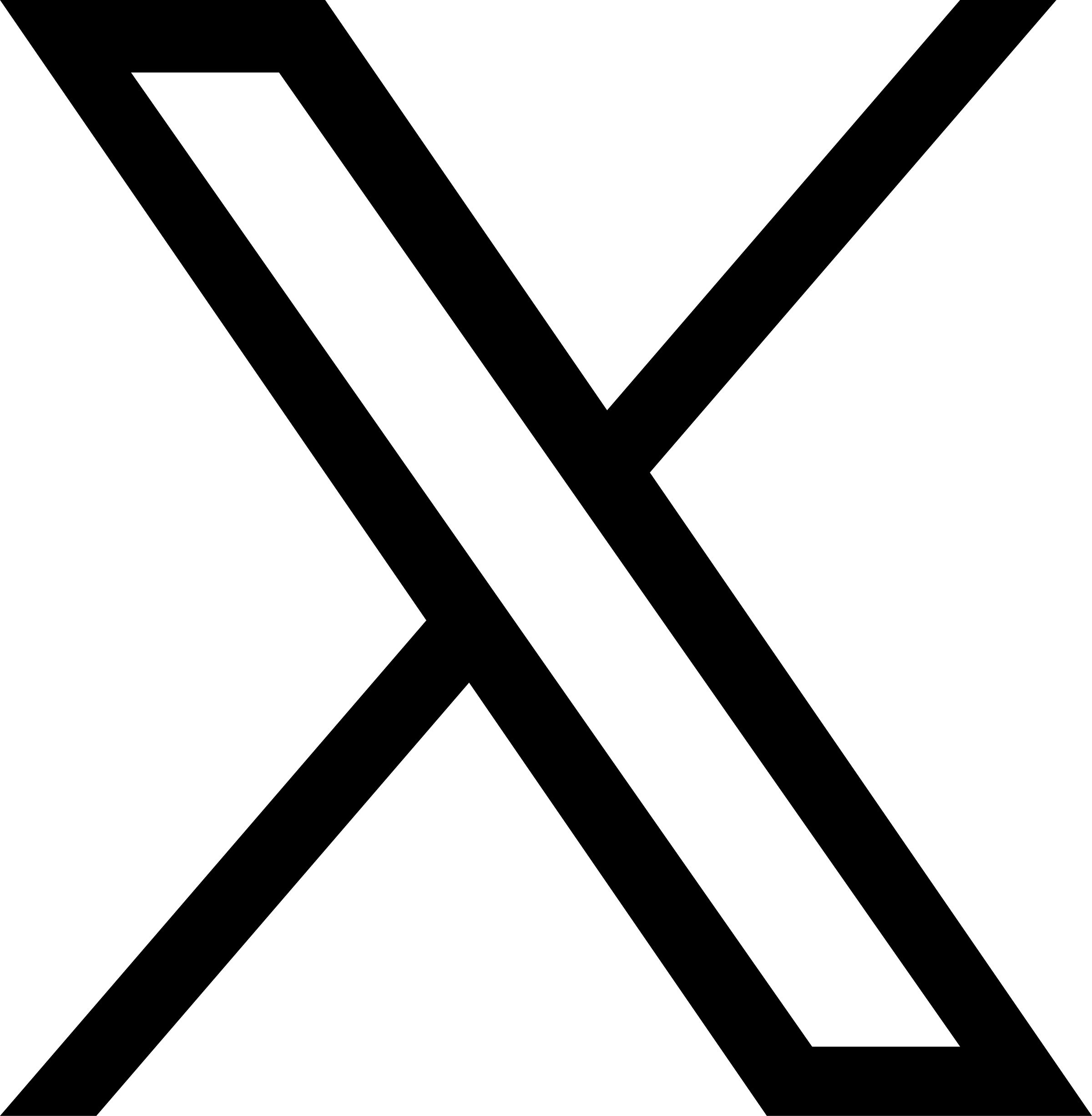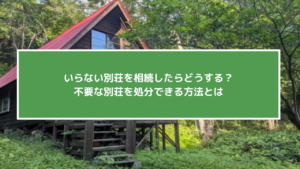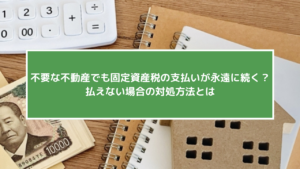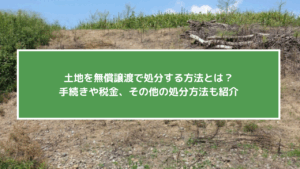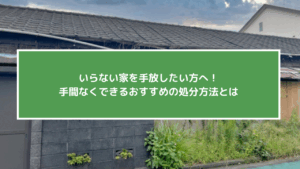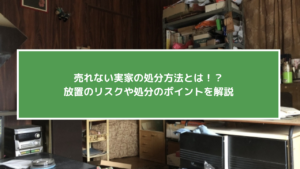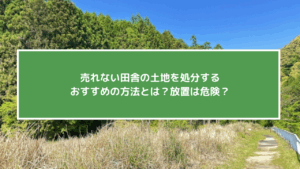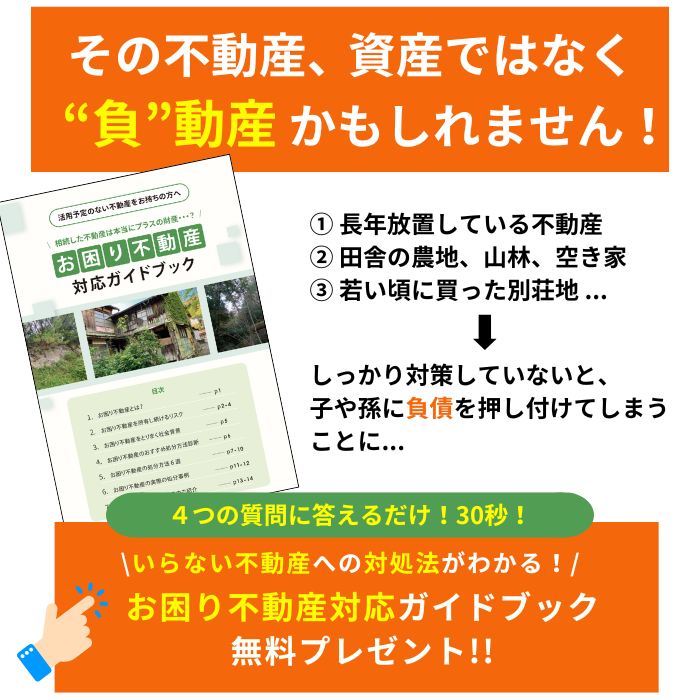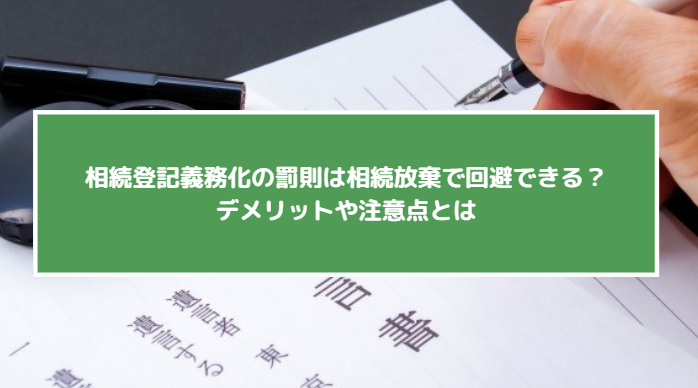
相続登記義務化の罰則は相続放棄で回避できる?デメリットや注意点とは
2024年4月1日から相続登記についての法改正が行われ、相続または遺贈によって不動産を取得した場合は、原則3年以内に法務局へ相続登記を申請することが義務化されました。正当な理由なく申請を怠った場合は、罰則が科される可能性があります。不要な土地を相続することになった場合、相続放棄を検討する方もいると思いますが、相続登記義務化の罰則は免除できるのかなど、疑問を持たれた方もいるのではないでしょうか。
本記事では、相続登記の義務化と相続放棄の関係、相続放棄をした場合の注意点や手続きについて詳しく解説します。不要な不動産を相続してしまい、対応に困っている方は、ぜひ参考にしてください。
相続登記とは

相続登記とは、土地や建物などの不動産の所有者が亡くなった際に、故人の不動産名義を相続人に変更する手続きのことです。
相続登記をしなくても、相続自体は行われますが、登記をしないと不動産についての権利を第三者に主張したり、売却することができません。相続登記を完了することで、始めて不動産についての権利を行使することが可能となります。
2024年度より相続登記は義務化
2024年4月1日から、相続登記の義務化がスタートしました。これにより、原則として不動産の相続を知った日から3年以内に、相続登記の申請をすることが法律上の義務となりました。また、相続登記の義務化は、過去に発生した相続にも適用されます。正当な理由なく、相続登記を期限内に行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。そのため、まだ相続登記が済んでいない不動産を所有している方は、手続きを行う必要がある点に注意しましょう。
相続登記が義務化された背景として、不要な不動産を相続したくない、相続人間で合意が得られないといった理由で、相続登記が適切に行われず、所有者不明土地が増加したことがあげられます。そのため、今後は相続登記を行わないことについて、これまでより厳しく罰則が適用される可能性があります。
相続人申告登記で罰則は回避できる

相続登記の義務化に伴い、「相続人申告登記」という新制度がスタートしました。相続人申告登記は、通常の相続登記が難しい場合に、より簡易的な手続きで相続登記の義務を果たせるように創設されたものです。
期限内(3年以内)に相続登記の申請をすることが難しい場合に簡易に相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みとして、「相続人申告登記」が新たに設けられました。
相続登記は、相続人全員の合意が必要だったり、必要書類を集めなくてはいけないため、登記をしたくてもできない場合もあります。そういった場合に、相続人申告登記を行えば、相続登記の申請義務を果たしたものとみなされ、罰則を回避できます。
ただし、相続人申告登記は、不動産の相続人であることを明示する手続きで所有権の移転は伴わないため、相続人申告登記をしても第三者に権利を主張したり、不動産を売却するといったことはできない点に注意しましょう。
相続放棄とは?
相続放棄とは、故人の財産を一切相続しないという意思表示のことです。もし相続に不要な土地が含まれていた場合、相続放棄をすることで、相続を回避できます。ただし、相続放棄をすると、いらない不動産だけでなく、預貯金や有価証券等もすべて相続しないことになります。
そのため、もし故人に財産があり、相続することで資産が増えるといった場合には、相続放棄を選択すると損をするケースがあるため、相続後に土地を処分する方法を考えることをおすすめします。
相続放棄をすれば相続登記の義務から逃れられる?
相続放棄をすれば、その方は初めから相続人ではなかったことになります。そのため、不動産を取得することがなくなり、相続登記の義務も発生しません。
したがって、故人に多額の借金がある場合や、どうしても相続したくない不動産がある場合には、相続放棄は有効な選択肢となります。
相続放棄をする際の注意点とは

相続放棄は有効な手段ですが、いくつかの重要な注意点があります。手続きを進める前に、これらのデメリットやリスクを十分に理解しておくことが大切です。
相続放棄には期限がある
相続放棄の手続きには、期限が定められています。原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。この期間を過ぎてしまうと、相続放棄は認められず、単純承認(すべての財産を相続すること)したものとみなされてしまうため注意しましょう。
相続放棄をしても不動産の管理義務が残る場合がある
相続放棄を選択する場合、不要な不動産の税金や管理・管理の負担を避けたいと考えている方も少なくないと思います。しかし相続放棄をしたとしても、不動産の管理義務が残ってしまう場合があります。
民法では、相続放棄時点で不動産を占有しているとみなされた場合、自己の財産と同様の注意を払って保存する義務があると規定されています。
民法第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
引用:e-Gov 法令検索「民法」
たとえば、不動産の場合は物件に住んでいたり、倉庫として利用していたといった事実があった場合、占有とみなされる可能性があります。相続する不動産について、占有にあたるかどうか不安がある場合、弁護士等の専門家に相談してみることをおすすめします。
相続放棄の手続き方法とは

相続放棄は、正しい手続きで行わなくては無効となる可能性があります。ここでは、一般的な相続放棄の手続きについて解説します。
1.財産調査
相続放棄を検討する場合、まず初めに故人の財産を正確に把握するための財産調査を行います。預貯金、有価証券、不動産といったプラスの財産だけでなく、借入金やローン、未払金などのマイナスの財産も含め、すべてを調査するようにしましょう。この調査結果をもとに、相続放棄をするべきか、それとも相続を選択するかを判断します。
2.必要書類の準備
次に、家庭裁判所に提出するための必要書類を準備します。
一般的に必要となるのは、下記の書類です。
・個人の住民票除票又は戸籍附票
・申述人の戸籍謄本
故人との関係性によって、追加の書類が必要になる場合があります。必要書類が不明な場合は、事前に管轄の家庭裁判所に確認しておくとよいでしょう。
3.申述書の作成、提出
必要書類が揃ったら、相続放棄の申述書を作成します。申述書には、申述人の情報、故人の情報、相続を知った日、相続放棄をする理由などを記載します。裁判所のウェブサイトで書式や記載例を入手できますので、参考にしながら正確に記入しましょう。
作成した申述書と必要書類を、管轄の家庭裁判所に提出します。提出方法は、直接持参するか、郵送でも可能です。
4.手続きの完了
申述書を提出し問題がなければ、家庭裁判所から申述人宛に「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。また、場合によっては相続放棄の意思を確認するための「相続放棄申述受理照会書」が届く場合もあります。その場合は、質問事項に回答し、返送しましょう。相続放棄申述受理通知書を受け取った時点で、相続放棄の手続きは正式に完了となります。
相続で不要な土地を処分するおすすめの方法とは

相続に不要な土地が含まれる場合、相続人にとっては税金の支払いや土地の維持、管理などが大きな負担となります。相続財産に資産があり、相続放棄を選択しない場合は、不要な土地であっても引き受けなくてはなりません。ここでは、相続した不要な土地を処分するための方法を紹介します。
不動産会社に依頼する
不要な土地がある場合、不動産会社に売却を依頼する方法が一般的です。立地や条件が良ければ、買い手が見つかる可能性があります。
すぐに売却したい場合は不動産会社に直接買い取ってもらう「買取」、希望の価格でじっくり売りたい場合は買主を探してもらう「仲介」を選択するといいでしょう。ただし、相続において不要と感じるような土地の場合は、資産価値がないとみなされ、そもそも取引の対象としてもらえない場合もあります。
相続土地国庫帰属制度を利用
2023年4月に始まった相続土地国庫帰属制度は、相続した不要な土地を国に引き取ってもらう制度です。一定の要件を満たす土地であれば、審査手数料と負担金を納付することで、国に所有権を移すことができます。
ただし、引き取ってもらえる土地には条件があり、建物が建っている土地や、境界が不明確な土地などは対象外となります。すでに不動産会社に依頼を断られている土地の場合は、相続土地国庫帰属制度の対象にならないケースもあるため、まずは最寄りの法務局に相談してみましょう。
近隣住民に譲渡
不要な土地の処分方法として、近隣住民に譲渡する方法もおすすめです。売却が難しい土地であっても、隣地の所有者であれば、自身の土地と一体で利用できるなどメリットがあるため、譲渡を検討してくれる可能性があります。
連絡先がわからない場合は、法務局で登記謄本を取得することで、住所を調べることができます。個人間の取引となるため、後々のトラブルを避けるためにも、契約書の作成や登記手続きは司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
引取サービスに依頼
不要な土地をどうしても処分できない場合は、専門の引取サービスへの依頼を検討しましょう。引取サービスは、不要な土地の活用に関する独自のノウハウをもっているため、他の方法で断られてしまった土地であっても、引き取ってもらえる可能性があります。
ただし、不動産の引取サービスはまだ法整備が追いついておらず、引取とみせかけて他の詐欺に誘導するといった会社もあります。依頼をする際は、信頼できる業者かどうかをよく確認の上、依頼するようにしましょう。

マッチングサイトを利用
最近では、マッチングサイトを利用して土地を処分する人も増えています。マッチングサイトは、土地を「買いたい人」と「売りたい人」をつなぐプラットフォームです。
マッチングサイトを使えば、自由な価格で不動産の情報を全国に発信でき、他の方法では売却できなかった土地でも、ニッチな需要を持つ買主が見つかる可能性があり、通常の不動産市場では売れないような土地でも取引が成立する場合があります。
不要な不動産に困っているという方は、まずは登録だけでも試してみることをおすすめします。
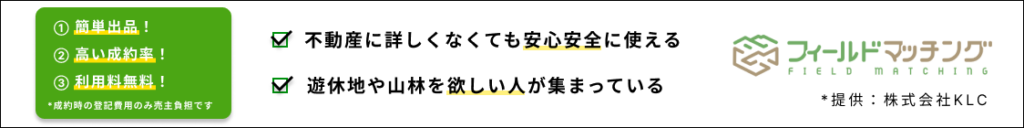
まとめ
2024年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく怠ると過料が科される可能性があります。相続放棄をすれば、この相続登記の義務からは逃れられますが、預貯金などのプラスの財産もすべて手放すことになり、一度手続きをすると撤回はできません。
どの方法が最適か判断するのが難しい場合は、相続に詳しい司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家のアドバイスを受けながら、ご自身の状況に最も合った選択を検討してください。
 監修者
監修者
株式会社KLC 代表 小林 弘典
幼少期から不動産が大好きな、自他共に認める不動産マニア。
不動産会社でも手を出せない不動産の専門会社「株式会社KLC」代表を勤め、
自身のYoutubeチャンネル「相続の鉄人」にて、負動産問題について啓蒙活動も実施。
- 総務省 地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業登録アドバイザー
- 空き家等低利用不動産流通推進協議会 理事
- 立命館大学経済学部 客員講師
- 不動産有料引取業協議会 代表理事